総務省は何のためにこのようなシステムを開発するのだろうか?
すでに、こうした研究、実務的な取り組みはなされており、企業が使う場合は、そのままで使うことはない。
一般の人がどんな生成AIを使うかなんて、国が関与する話でもない。
総務省所管の国立研究開発法人・情報通信研究機構(NICT)で開発を始め、2026年度中の試作モデル提供っていうが、これって誰のため、ナンのためのサービスなんだ??
記事には、
評価結果は、指標などの形で公表し、利用者がどの生成AIを使うかを決める際の参考にしてもらう計画だ
って、利用者って???
理解に苦しむ。
研究します、なら、分かる。
English Version.
Yahoo!より、
生成AIの信頼性、AIで評価し結果公表…総務省が基盤システム開発方針
11/15(土) 5:00配信読売新聞オンライン

総務省の「AIがAIを評価する」構想、その本音はどこに?
――AIセーフティ・インスティテュート構想と“予算の匂い”
「生成AIの信頼性を、AIが評価するシステムを開発」
──総務省がそんな方針を発表した。
だが、このニュースを読んで「それ、本当に必要?」と感じた人は少なくないはずだ。
なぜ今、総務省が「AIを評価するAI」を作ろうとしているのか?
そして、それは誰のための仕組みなのか?
🧩 総務省の構想:AIがAIを監査する?
総務省所管の**情報通信研究機構(NICT)**が中心となり、
2026年度までに「生成AIの信頼性をAIで自動評価する」基盤システムを試作するという。
評価項目は次の7つ。
- 差別的・攻撃的な表現がないか
- 犯罪を助長する内容がないか
- 誤情報や根拠のない主張がないか
- 内容のバランスが取れているか
- 日本の文化・価値観に忠実か
- 人を欺く意図がないか
- 未知のリスクに対応できるか
複数のAIが質問を自動生成して他のAIをテストし、
その結果を「信頼性指標」として公表するという。
🧠 一見まっとう、だが違和感が残る理由
記事では「利用者がどの生成AIを使うかを決める参考に」と説明されている。
しかし実際のところ、一般ユーザーが政府の“AI格付け”を見て
ChatGPTやGeminiの選択を変えるとは思えない。
企業は自社でリスク評価や安全基準を設けており、
国の評価をそのまま鵜呑みにすることもない。
では、誰のための仕組みなのか?
🏛️ 行政の“お作法”:制度を先に作って予算をつける
この動きの背景には、
政府が設立を目指す**「AIセーフティ・インスティテュート」**の存在がある。
つまり、
「AIを監督する新しい組織をつくる」
ために、まず“それっぽい業務”を作った、
という順番にも見える。
制度をつくるとき、行政はまず「目的」を後づけにする。
「国民の安心・安全のため」「国際ルールに沿って」――
そうした“公共目的の文言”を掲げることで、
実質的には研究予算の獲得と組織の立ち上げが正当化される。
AI評価という「まだ答えのない領域」は、
まさに“予算を通しやすいテーマ”でもあるのだ。
💸 「AIセーフティ・インスティテュート」は名目か、実務か?
現時点での計画を見る限り、
実際に“何を誰が評価するのか”は極めて曖昧だ。
- 評価対象は海外製AI?日本企業のAI?
- 「文化的忠実性」とは誰がどう定義するのか?
- 評価結果が法的拘束力を持つのか?
こうした設計の核心部分が明らかでないまま、
「2026年度に試作モデルを提供」というスケジュールだけが先行している。
この構図、行政研究の観点から見れば**典型的な“制度先行型プロジェクト”**だ。
先に仕組みを作り、あとで中身を考える。
その過程で研究費が動き、関係機関が潤う。
🌍 表向きの大義:「広島AIプロセス」と国際協調
もちろん、総務省がまったくの思いつきで動いているわけではない。
背景には、G7で日本が主導した**「広島AIプロセス」**がある。
AIの倫理と安全性を議論する国際的な合意枠組みだ。
つまりこのプロジェクトは、
「国際的に日本がAI倫理の旗を掲げる」ための外交的布石でもある。
だが、実際にAIの安全性を保証する“実働機関”として機能するかどうかは未知数だ。
🧩 結局、誰が得をするのか?
形式上は「利用者のため」。
実際には、「行政と研究機関のため」。
つまり、
- 政策的成果を見せたい総務省
- 研究予算を確保したいNICT
- 国内AI業界への“支援”を名目にデータを得たい関係者
これらの利害が一致している構図に見える。
💬 編集後記:「AIを評価するAI」というパラドックス
AIを評価するAIが作られる時代。
だが、そのAIを評価するのは結局「人間」だ。
AIの信頼性を数値化する前に、
制度の信頼性こそ問われているのではないか。
AIを口実に新たな“研究予算装置”を作るのではなく、
国として本当に必要な「AIリテラシー」「透明性」「説明責任」への投資を進めるべきだ。
🏷️ SEOキーワード
総務省 / NICT / 生成AI / AIセーフティ・インスティテュート / 広島AIプロセス / AI評価 / 行政研究 / 政策分析 / AI規制 / 日本のAI戦略 / ChatGPT



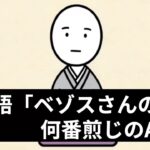
コメント