国際基準で大学も評価される。
これはその研究レベルが国際的に通用するかということ。
インターネットが普及した現代では、英語での情報発信が必要。論文も海外で読まれなければ意味がない。そうした研究環境を備えているかどうかが判断基準となる。
ボーダーの議論では、旧帝大とう7大学があるが、その中で北大、九大は脱落した形。
Yahoo!より、
だから早慶は“準一流”大学…結局、どこまでが一流なのか「阪大、東北大はボーダー」元経済誌元編集長が重視する「国際基準」
5/10(土) 9:10配信MINKABU

早慶、国際的評価では国立上位校に及ばない
大学ランキングは単なる順位ではなく、予算や人材の集まり方にも影響する。ランキングで上位に入る大学は、国の研究費や企業からの研究依頼、海外の大学との連携機会などでも優遇される。一度上位に入ると有利な立場を維持しやすくなる一方で、一度外れると再び上がるのが難しくなるという仕組みがある。 東京大学と京都大学は、入試の難しさ、研究成果、研究資金の面で他の大学より明確に上にある。一橋大学と東京工業大学は特定の分野に強く、国際的にも専門性で高く評価されている。東北大学、名古屋大学、大阪大学は、規模や研究体制、制度面で必要な条件を満たしている。早稲田大学と慶應義塾大学は私立の代表として、入試の厳しさや卒業生の社会的影響は大きいが、研究の国際的評価では国立の上位校には及ばない。 世界ランキングで150位以内という目安を使えば、日本の大学で一流と呼べるのは、東京大学、京都大学、東京工業大学、一橋大学、東北大学、大阪大学、名古屋大学の7校にしぼられる。これらは、研究力、教育体制、教員と学生の構成、制度の安定性といった面で、国際的な基準に照らしても高水準にある。早慶などそれ以外の大学にも分野や地域で強みはあるが、国際的には「準一流」あるいは「国内上位」にとどまっている。 一流大学という言葉は、過去の名声や世間のイメージだけでは定義できない。研究の影響力、入試の難易度、継続的な制度支援、学生の社会的背景など、幅広い実証的な基準にもとづいて評価されるべきである。日本の大学が国際的な評価の中で一流の立場を保つには、たえず改革を続け、海外の大学や研究者と連携し続ける姿勢が求められる。
コメント(日本語):
国際基準で見た「一流大学」が7校に絞られるというのは、現実的でありながら、日本の大学界の課題を端的に示しています。研究レベルの国際的評価は、英語での論文発表や海外からの引用数、共同研究の実績など、可視化可能なデータで判断される時代です。旧帝大の中でも北海道大学や九州大学が外れるという結果は、単に歴史や規模だけではなく、国際競争力が厳しく問われていることを物語っています。
国内での知名度や就職実績とはまた別の「研究大学」としての実力が問われており、これは今後の大学改革において非常に重要な視点になるでしょう。
Comment (English):
The fact that only seven Japanese universities are considered “world-class” by international standards clearly highlights the current challenges in Japan’s higher education system. Global university rankings increasingly prioritize measurable factors such as research output in English, citation impact, and international collaboration. The exclusion of Hokkaido and Kyushu Universities from this elite list suggests that historical prestige or scale alone is no longer sufficient—what matters is actual global competitiveness.
It’s a sharp reminder that institutional reputation within Japan differs from international research standing, and future reforms must focus on bridging that gap.



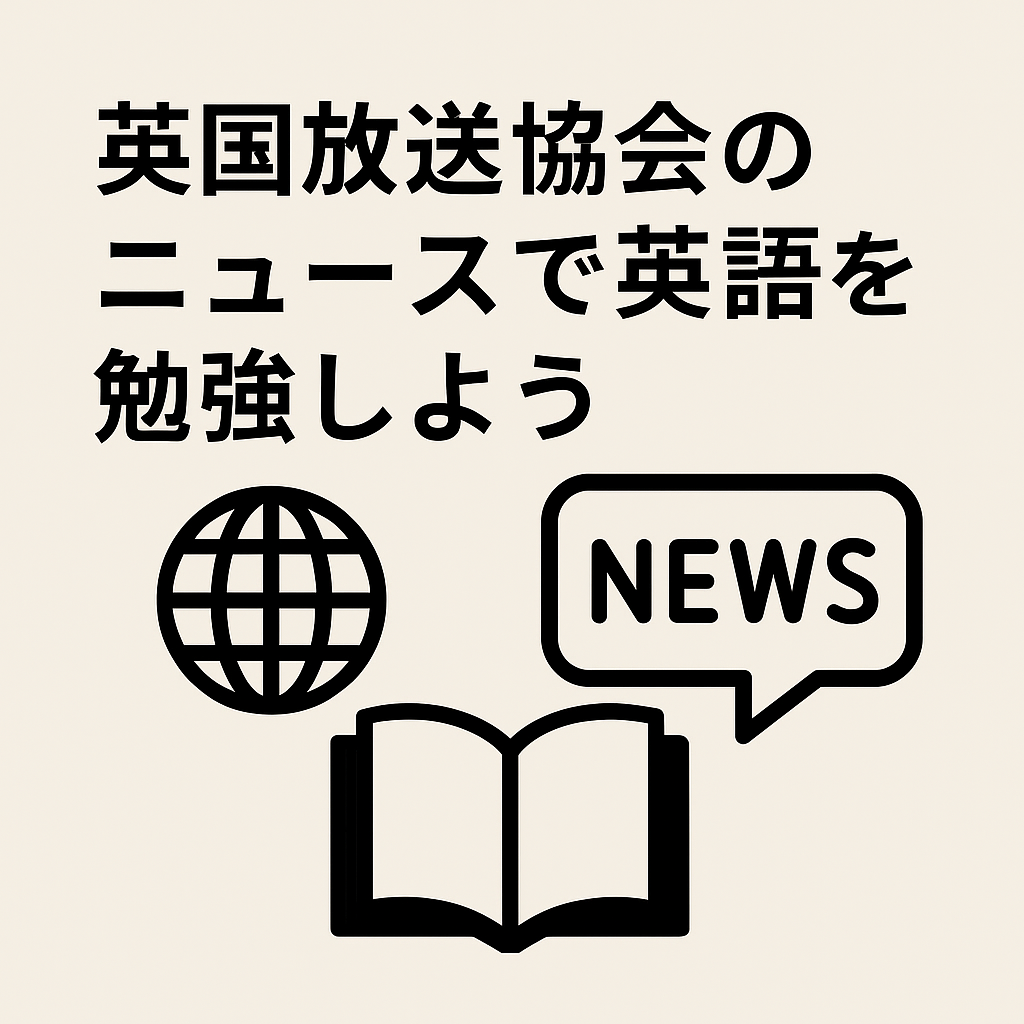
コメント