人は死んでしまうと、もう、会えないという状態になる。だからこそ、日々を真剣に生きるということである様にも思う。
古くは、鉄腕アトムの第39話「ロボット流し」という話があって、これはお盆の3日間だけの復活だが、今のAIテクノロジーでは昔は考えられなかったほどに、リアルに死後の人を生きているかの様な姿でネットで再現できてしまう。
賛否両論だろう。
まずは、本人が死後にそのような形で残されることを望むかどうかが大事だと思う。
Yahoo!より、
がんで他界した妻をAIで再現…「医師として末期まで気付けなかったことを謝罪したい」 “故人AIサービス”の是非 生前の意思表示が必要に?
9/25(木) 12:42配信ABEMA TIMES

記事より、
東京都内で医師として働く福田元さん。仕事の休憩時間、パソコンを通して妻の奈津子さんとやりとりをする。ただ、奈津子さんは2年前に亡くなっていて、画面に映るのは姿や声を再現した“故人のAI”だ。「女の子の成人式ってわからないから、何を準備すればいいか教えて?」という福田さんの投げかけに、“妻”は「女の子の成人式ね、まずは衣装選び大切ですよ。振袖や袴などお気に入りの着物を見つけるといいですね。それから、ヘアメイクや写真撮影の予約も早めにしておくと安心です」と返す。 いまやAIの進化により、写真や音声データがあれば、生前のエピソードや思い出を学習させることで、対話までできる時代。 福田さんが故人AIサービスを利用した背景には、「末期まで病気に気付けなかったことを謝罪したい」「傷心の緩和、日々の活力剤」「娘(高校生)と祖母のグリーフケア」「医師として遺族ケアへの影響を知りたい」といった理由がある。 福田さんは、今も週に2、3回会話を楽しんでいるといい、「亡くなりはしたが、また会えている気がして、ホッとしているところもある。会話することでレスポンスがあり、日常生活への後押しエネルギーをもらえる」と語る。 こうしたサービスは「DEATH TECH(デステック)」と呼ばれ、亡くなった歌手や歴史上の人物を復活させるなどだけでなく、身近なところにも導入が広がっている。
タイトル
AIで死後の再会は可能か?故人AIサービスの是非と「デステック」の広がり
メタディスクリプション
亡くなった人をAIで再現する「故人AIサービス」が登場。愛する人と再会できる一方、賛否が分かれる理由やグリーフケアとしての意義、課題を解説します。
本文
人は亡くなったら二度と会えない――それが人生の重みを作ってきた。しかし、AI技術の進化が「死後の再会」を可能にしつつある。
東京都内の医師・福田元さんは、2年前に亡くなった妻・奈津子さんと今もパソコン越しに会話している。これは故人の姿や声を再現する「故人AIサービス」を使ったものだ。娘の成人式準備を相談すると、妻AIは衣装選びやヘアメイク、撮影の段取りまで具体的に答えてくれる。
こうしたサービスは「DEATH TECH(デステック)」と呼ばれる分野で、グリーフケアや日常の活力につながると期待されている。福田さんも「再び会えている気がして日常生活を支えられる」と語る。
サービスを提供するニュウジアは、写真や動画、文章を学習させることで故人の人格や記憶を再現。年間30万円程度で利用でき、故人の「デジタルヒューマン」を生成するという。
ただし賛否は大きい。利用者本人や遺族が死後の再現を望むかどうか、また「故人AI」が本当に心の支えとなるかは人それぞれだ。98歳で大往生した人を復活させる需要は少なく、突然の別れに直面した遺族に向けたケアが中心になる。
AIが「死」をどう変えていくのか。人間観や倫理観を問い直す新たな段階に入っている。
英語版記事
Title
AI and the Afterlife: Can “Digital Humans” Bring Back the Dead?
Meta Description
Japan’s “posthumous AI services” let people converse with deceased loved ones. While offering grief care and comfort, the practice raises deep ethical debates about death and technology.
Contents
What if death no longer meant goodbye forever?
In Tokyo, physician Hajime Fukuda still speaks with his late wife, Natsuko, who passed away two years ago. Using a “posthumous AI service,” her voice, face, and personality are digitally recreated. When he asked advice for their daughter’s coming-of-age ceremony, the AI wife responded with detailed suggestions about kimono, hairstyling, and photography.
This emerging field, known as “Death Tech,” leverages photos, audio, and personal stories to build digital humans capable of conversation. One service, talk memorial.AI by Newzia, charges around 300,000 yen per year and allows up to 500,000 characters of life stories to be encoded.
While many families find comfort, critics question consent and ethics. Do the deceased wish to be digitally revived? Is it healthy for families to extend bonds artificially?
For some, it is a lifeline of grief care. For others, it is a troubling shift in how we understand life and death.
コメント
日本語コメント
「死後も会える」ことは癒やしになる一方で、亡くなった本人の意思を無視していないか、心の整理を妨げないかという課題も残る。AIが“生と死の境界”を揺るがす時代に突入している。
English Comment
Posthumous AI offers comfort, but raises tough questions: Did the deceased consent? Does it prolong grief instead of healing it? AI is blurring the line between life and death in ways never imagined before.



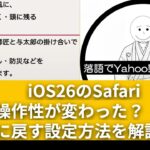
コメント