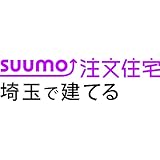空き家という数字の半分は賃貸住宅の空き家。
賃貸住宅は投資物件であり、賃貸なので入れ替えのための空き状態はある。
それをことさら取り上げるのはどうか?
人が減って広い家に住めるとなった瞬間に区画割りを替えなければならなくなる。
つまり家を移動させるか、壊して作るということが必要になる。
お金があって建て直せるなら建て直した方が一般に性能の高い住宅ができる。
それが悪いことか?
yahooより。
「空き家」そのまま…増え続ける新築住宅 人口減少局面で裏目に
SankeiBiz 2月9日(月)6時36分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150206-00000510-fsi-bus_all
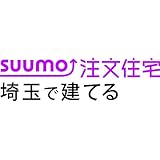 |
|
新品価格 |
![]()
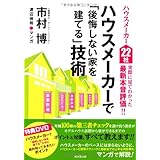 |
|
新品価格 |
![]()
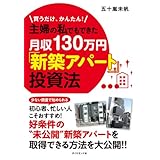 |
|
買うだけ、かんたん! 主婦の私でもできた月収130万円「新築アパート」投資法 新品価格 |
![]()
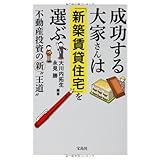 |
|
新品価格 |
空き家の増加を尻目に日本の住宅数は毎年増え続けている。1998年以降の着工戸数(建て替えも含む)は毎年100万~120万戸。2013年度は消費税率引き上げ前の駆け込み需要もあり98万戸が着工された。全住宅取引の8割以上は新築で、中古住宅の比率は10%半ばに留まっている。欧米で7~9割を中古が占めるのとは対照的だ。なぜ日本は新築比率が高いのか。富士通総研の米山秀隆上席主任研究員は「第二次世界大戦後の住宅政策の影響が大きい」と指摘する。
敗戦後の日本は市街地が焼け野原になったうえ、外地からの復員者も増えて住宅が圧倒的に不足していた。政府は住宅建設を行うため、あいまいな線引きのまま農地も宅地に転用して、無秩序に市街地を広げていった。1950年代には高度成長による建設ラッシュが起きた。都市部を中心に人口が急増し、東京や大阪の近郊にニュータウンが建設された。政府は持ち家制度を奨励し、住宅金融公庫(現・住宅金融支援機構)が低利融資を行い、住宅ローン減税のしくみも作った。
量の確保が最優先で、質の良い建材を用いて手入れをしながら長く使うという戦前の住宅建設の概念は後回しだ。地価は右肩上がりに上昇し、建物に価値はなくても土地の価値は残るため、早期に住宅を取得することが有利とされた。住宅総数は60年代後半に総世帯数を越えた。やがてバブルが崩壊し、世の中が不動産価格は必ず値上がりするという「土地神話」の夢から覚めても、政府は一貫して住宅建設の後押しを続けた。
住宅はてっとり早い公共投資だ。道路やダムなどのインフラ整備には膨大な時間やお金がかかるが、住宅は建ぺい率や容積率の制限を緩和すればいい。住宅着工は建築関係の仕事を生むし、家電や家具など消費も刺激するから、効率の良い景気対策になる。昨年末の緊急経済対策には、住宅エコポイント制度の2年半ぶりの再開が盛り込まれた。・・・
―批判するのだが、解決はない。
一世帯が複数の家をもって活用する、ということを考えれば世帯に対して箱である住宅数が多いから無駄というような短絡的な話ではなくなる。
店にしてもいいし、倉庫にしても、書斎にしてもいいではないか?
短期的な貸家にするのもいいだろう。
要は使い方なのである。
新しい家を欲しがるのはおかしいとか、ダメとかいう話ではないだろう。