消費税の廃止や減額は経済的に効果が高いという。
だが、以下の記事にもあるように、具体的にどう適用するかが問題。
日本人のサラリーマンの多くは税申告は会社任せなので無頓着だが、必ず確定申告することが望ましい。
その際に、消費税分を税額控除することで対応できないか?
キャッシュレス決済にすることで、事務手続きを簡素化するなどの方法が取れるだろう。
高齢者もLINEを使う時代。そろそろ、電子決済(クレジットカードの利用含む)などの恩恵が享受できるような社会にすることが必要だろう。
Yahoo!より、
<独自>食料品の消費税率0% 立民が参院選公約に盛り込む 25日に正式決定
4/24(木) 22:52配信 産経新聞
記事より、
立憲民主党は夏の参院選公約に時限的な食料品の消費税率0%を盛り込む。25日の臨時役員会で正式決定する。党内では消費税減税を求める減税派と、慎重な財政規律派が論争していたが、物価高の中で選挙戦を戦うには減税が有利だと判断した。 【ひと目でわかる】枝野氏の「分党発言」に党内の反応は… 立民内は消費税に関し、時限的に食料品の消費税率を0%にする案のほか、▽消費税率を一律5%に引き下げる▽中低所得者の消費税の一部を税額控除し、控除しきれない分を給付する「給付付き税額控除」も検討していた。公約に盛り込む案に関し、食料品の消費税を0%にした後、給付付き税額控除に移行するとしている。
🇯🇵 日本語のコメント:
食料品の消費税0%?本当に実現できるのか。
立憲民主党が夏の参院選の公約として、**食料品の消費税を時限的に0%**にする方針を示したとのこと。確かに、物価高の中での減税は庶民の生活支援として歓迎される政策ですが、実行面には疑問も残ります。
実際、消費税をどうやって「誰に」「どのように」減免するかという具体策が必要です。中でも、「給付付き税額控除」や「税額控除」による仕組みは有効かもしれませんが、日本のようにサラリーマンの多くが確定申告をしない社会では、申告不要型の簡素な仕組みが求められるでしょう。
例えば、キャッシュレス決済によって自動的に食料品支出を記録・還付する仕組みなどが考えられます。LINEを使いこなす高齢者も増えている今、電子決済と減税を結びつける政策は現実味を帯びてきています。
ただし、減税だけで終わらせず、その後の財政的な持続可能性や、社会保障との整合性も見据えた制度設計が必要です。
🇬🇧 English Comment:
Zero consumption tax on food? A promising idea—but can it work?
Japan’s opposition party, the Constitutional Democratic Party (CDP), is reportedly planning to include a temporary 0% consumption tax on food in its platform for the upcoming Upper House election. While this move may appeal to voters amid rising prices, its practical implementation raises several challenges.
One major issue lies in how such a policy would be applied and tracked. Many Japanese salaried workers do not file their own tax returns, so relying on tax deductions or rebates could leave out a large portion of the population.
One possible solution could be to tie cashless payment methods to tax refunds—automatically tracking food purchases and issuing refunds or deductions accordingly. With more elderly people using smartphones and apps like LINE, digital systems that connect tax benefits to payment methods may become more viable.
However, the proposal must be coupled with a long-term fiscal plan to ensure sustainability and alignment with Japan’s social security systems.


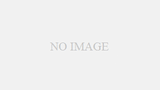
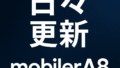
コメント